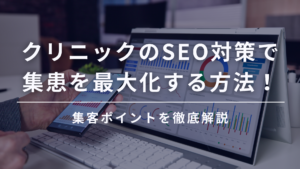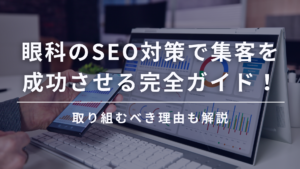記事執筆の方法とは?依頼する場合の流れやライター選び・メリットまで徹底解説

Webサイトの集客力を高めたい、でも何から手をつければ良いかわからない…そんな悩みを抱えていませんか?
質の高い記事は、検索エンジンからの評価を高め、多くのユーザーをあなたのサイトへ導いてくれます。
しかし、効果的な記事を執筆し、継続的に発信し続けるのは簡単なことではありません。
「記事執筆の具体的な手順がわからない」「外注したいけど、誰に頼めばいいのか不安」と感じている方も多いでしょう。
この記事を読めば、記事執筆の基本から、失敗しない外注先の選び方、さらには執筆を効率化するテクニックまで理解できます。


記事執筆とは?
記事執筆とは、単に文章を作成する作業ではありません。
読者が抱える疑問や悩みを解決し、最終的には自社のビジネス目標達成につなげるための重要なマーケティング活動です。
検索エンジンからの集客を目的とするSEO記事や、商品の魅力を伝えるコラム記事など、その目的は多岐にわたります。
読者は何らかの「知りたい」「解決したい」という目的を持って記事を読みに来ます。
そのため、書き手の自己満足で終わるのではなく、常に読者の視点に立ち、有益な情報を提供することが記事執筆の本質です。
具体的には、設定したキーワードの検索意図を深く理解し、その答えを分かりやすく、かつ論理的に示す必要があります。
優れた記事は、読者に満足感を与えるだけでなく、企業の専門性や信頼性を高め、見込み顧客との良好な関係を築く土台となります。
つまり、記事執筆はWeb上で見込み客とコミュニケーションを取り、ファンになってもらうための強力なツールなのです。
記事執筆の流れ【準備〜公開】
ここでは全工程を五段階に分解し、つまずきやすい要素と対策を詳細に解説します。
まずは全体像と学習メリットを把握し、ご自身のケースに置き換えて読み進めてください。
Step1.キーワード選定
記事執筆の成否を左右するのが、最初のステップであるキーワード選定です。
キーワードとは、読者が検索エンジンで情報を探す際に打ち込む単語のことで、これを選ぶ作業が記事の方向性を決定づけます。
読者がどのような言葉で検索するかを予測し、自社のビジネスやターゲット層に合致したキーワードを選ぶことが重要です。
例えば、「記事執筆」という大きなテーマだけでなく、「記事執筆依頼方法」「記事執筆コツ初心者」といった、より具体的なキーワードを狙うことで、読者の悩みにピンポイントで応えることができます。
適切なキーワードを選定することで、検索結果の上位に表示されやすくなり、記事を届けたいターゲット層に効率的にアプローチできます。
逆に、この選定を誤ると、どれだけ良い記事を書いても誰にも読まれないという事態に陥りかねません。
Step2.競合調査と構成
キーワードが決まったら、次に行うのが競合調査と構成案の作成です。
これは、記事の設計図を作る極めて重要な工程です。
まずは、選定したキーワードで実際に検索し、上位に表示されている競合記事がどのような情報を、どのような順序で提供しているかを徹底的に分析します。
読者がどのような情報を求めているのか、どのような切り口が評価されているのかを把握することが目的です。
その分析結果をもとに、自社の記事が競合よりも価値のある情報を提供できるよう、見出しの構成案を作成します。
読者が求める情報を網羅しつつ、自社ならではの知見や独自の視点を加えることで、オリジナリティの高い記事構成を目指しましょう。
この設計図がしっかりしていれば、執筆作業がスムーズに進むだけでなく、内容のブレも防げます。
Step3.取材・情報収集
構成案が完成したら、次はその骨組みに肉付けしていくための情報収集です。
記事の説得力や信頼性は、情報の質によって大きく左右されます。
常に一次情報や信頼性の高い情報源を当たることを心がけましょう。
公的機関の発表、専門家の論文、独自の調査データなどがそれに該当します。また、テーマによっては専門家へのインタビューや、自社サービスの利用者へのアンケートなども有効な手段です。
インターネット上の情報を参考にする際は、複数のサイトを比較検討し、情報の正確性を必ず確認してください。
不正確な情報を発信してしまうと、読者の信頼を失うだけでなく、企業の信用問題にも発展しかねません。質の高いインプットが、質の高いアウトプットにつながるのです。
Step4.ライティング・編集
いよいよ、収集した情報と構成案をもとに本文を執筆するライティングの工程です。
ここでは、読者がストレスなく読み進められる分かりやすさが求められます。
文章を書く際は、「結論→理由→具体例→結論」の順で構成するPREP法を意識すると、論理的で分かりやすい文章になります。
専門用語は避け、平易な言葉で説明したり、具体例を挙げたりする工夫が重要です。
また、適度に改行を入れたり、箇条書きを活用したりして、視覚的な読みやすさも意識しましょう。
書き終えたら、必ず編集作業を行います。文章のリズムや流れを確認し、冗長な表現を削ったり、より伝わりやすい言葉に修正したりします。
客観的な視点で自分の文章を見直すことで、記事のクオリティを一段階引き上げることができます。
Step5.校正・公開後リライト
公開直後はインデックス促進が最優先です。
XMLサイトマップ送信、内部リンク追加、SNSシェアを同日に行い、クローラー巡回頻度を高めましょう。
Search Consoleで平均掲載順位が10位以内に入ったらタイトルCTRをABテストし、3か月後に本文を再評価して情報鮮度を向上させます。
YMYL領域ではガイドライン改訂のたびに追記し、法的リスクを下げます。
リライト対象は「CV貢献キーワード」「CTRが5%以上低下」「新サジェストが出現」の三条件で抽出し、優先度を設定してください。
改善タスクをNotionでカンバン化し、担当と期限を明確化すると運用が滞りません。
記事執筆の依頼方法
依頼形態を誤るとコストも品質も崩れます。
本章では四つの方法を比較し、状況に合った最適な選択ができるように解説します。
社内ライターで内製化
内製化の最大の利点は高速PDCAです。
部署横断で情報共有がしやすく、仕様変更にも即応できます。課題は採用・教育・評価のコストです。
新人が戦力化するまで平均6か月、教育工数は月40時間が目安となります。
成功事例ではOKRで目標を可視化し、コンテンツが売上の何%を支えるかを社内共有してモチベーションを維持しています。
フリーランスへ依頼
フリーランスのライターに業務委託する方法です。
必要なときに専門スキルを持つ外部ライターへ依頼できる柔軟性が最大のメリットです。
自社に専門の書き手がいなくても、得意分野を持つフリーランスを選べば質の高い記事を制作してもらえます。
また、案件ごとに契約できるため固定人件費を抱えずに済み、プロジェクト単位でコスト管理しやすい利点もあります。
依頼する際は契約条件の明確化が重要です。業務内容や納期、報酬、成果物の著作権帰属範囲などを盛り込んだ契約書や依頼書を取り交わし、双方の認識違いを防ぎます。
特に2024年施行の「フリーランス・事業者間取引適正化等法」により、発注者はフリーランスに業務委託する際に取引条件を書面で明示し、成果物受領日から60日以内に報酬を支払う義務が課されています。
これに沿って、氏名・住所・連絡先・業務内容・作業場所・報酬額など必要事項を契約書に明記しましょう。
また秘密保持契約(NDA)の締結や著作権の取扱い(後述)についても合意しておくことが望ましいです。
フリーランス依頼のデメリットとしては、外注管理やコミュニケーションの手間が発生する点、そして個々のフリーランスのスケジュールにより納期や対応が左右される点が挙げられます。
信頼できるフリーランスを選定し、契約条件をきちんと定めれば、専門性の高い記事を柔軟に発注できる手段となります。
記事作成代行サービス
代行会社はディレクター・ライター・校閲・デザイナーを内包し、ワンストップで高品質な記事を納品します。
大量発注時のスケールメリットと品質担保が強みですが、単価が高く契約縛りがある点が弱みです。
比較の際は「ライタープール規模」「専門ジャンル実績」「運用レポート頻度」を確認しましょう。
TriWinSEOライティングのようにAIと専門ライターをハイブリッドで運用するサービスなら、1記事1.5万円でも質と量を両立できます。

AIライティング併用
生成AI(ChatGPT、Claudeなど)を一次ドラフト生成に活用し、人間が校正・加筆で仕上げるワークフローは急速に浸透しています。
プロンプト体系化とファクトチェック体制を整えることで、制作時間を60%削減できます。導入ステップは次のとおりです。
- ガイドラインに違反する表現を正規表現で検出します。
- 社内外向けチェックリストをNotionで共有します。
- モデル更新履歴を管理し、出力差異を検証します。
海外メディアのVentureBeatはAI比率を40%まで引き上げ、年間で35万ドルを節約しました。
記事執筆のメリット・デメリット比較
選択肢ごとの違いを四軸で可視化し、意思決定を高速化しましょう。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 品質 | 専門家監修で検索順位と信頼性が向上 | 監修費用が増大し、スケジュールが遅延しやすい |
| コスト | AI併用で単価を3割削減可能 | 内製は人件費が固定費化 |
| スピード | 代行なら月50本以上の納品が可能 | フリーランス複数管理で遅延リスクが発生 |
| 運用負荷 | アウトソースで企画工数を削減 | 発注書作成と成果管理が必須 |
品質
品質はブランド価値に直結します。専門家コメントと公的統計、独自データを組み合わせてE‑E‑A‑Tを底上げしましょう。
ユーザーアンケートやサポートログを引用すると、信頼度が大幅に高まります。
コスト
コストは「制作費」「管理費」「修正費」に分解して把握します。
CPA(Cost Per Acquisition)を広告費と比較し、ROIを測定すると投資判断が容易です。
AI活用で単価が30%下がっても管理工数が増えれば総コストは上がるため注意が必要です。
スピード
スピードはトレンドKWを狙う際の生命線です。
ボトルネックを特定し、重点的に対策することでリードタイムを10日から5日へ短縮できるケースもあります。
社内外のレビュアー数を減らすより、責任範囲を明確化するほうが品質を維持しつつ高速化しやすいです。
運用負荷
NotionやAsanaでプロセスを標準化し、タスク自動リマインドを設定すれば外注時の運用負荷を半減できます。
社内ナレッジベースに手順書を蓄積し、新人でも再現できる仕組みを整えてください。
記事執筆を依頼で失敗しないためのポイント
発注側の準備不足が失敗要因の8割を占めます。
本章では想定外をゼロにし、コスト超過を防ぐ具体策をご紹介します。
依頼書の書き方
依頼書には「目的」「ペルソナ」「想定キーワード」「禁止事項」「納品形式」の五項目をテンプレート化しましょう。
目的と評価指標を冒頭に明記すると、認識のずれが激減します。
SaaS企業A社はテンプレート導入後、平均修正回数を3.2回から0.8回へ削減しました。
ライター選定基準
「専門知識」「執筆再現性」「コミュニケーション速度」の三軸で選定します。
URL一覧に加え、成果指標(PV推移・CV件数)を必ず提示してもらい、質問対応速度をチェックすると実務での信頼度を測れます。
NDA・著作権
成果物の著作権譲渡、盗用禁止、第三者提供禁止を契約に盛り込みましょう。
医療や金融といった高リスク領域では、レビュー責任の所在を契約書に記載し、法的リスクを低減してください。
記事執筆のライター選びのコツ
優秀なライターはプロジェクトの成否を決める資産です。
見抜き方と口説き方を具体的に解説します。
必要スキルセット
SEO知識・構成力・取材力・データ分析の四技能を兼ね備える人材は上位3%にとどまります。
深掘り質問を用意し、過去に立てた仮説と結果を語れるかで実力を測りましょう。
料金体系
ライターの料金体系は、主に「文字単価」「記事単価」「時給制」の3つに分かれます。
文字単価(例:1文字2円)は最も一般的で、執筆文字数に応じて報酬が決まります。
記事単価(例:1記事10,000円)は、専門性の高い記事や調査に時間がかかる場合に用いられることが多い形式です。
時給制は、継続的な運用サポートやリライト業務などで採用されることがあります。
料金はライターの実績やスキル、記事の専門性によって大きく変動します。
相場を把握しつつも、安さだけで選ぶのではなく、求める品質と予算のバランスが取れたライターを探すことが重要です。
ポートフォリオ評価
URLだけでなく執筆背景・改善プロセス・成果指標をヒアリングします。
失敗事例を語れるライターは改善思考が高く、長期契約で価値を発揮しやすいです。
記事執筆の時間短縮テクニック
記事量産期に突入すると「とにかく時間が足りない」という課題が顕在化します。
本章では即効性のある三手法を解説し、どの体制でも再現できる運用モデルをご紹介します。
テンプレート活用
記事作成のたびに、毎回ゼロから構成や文章を考えるのは非効率です。
記事の構成案、導入文の型、まとめの締め方など、頻繁に利用する要素はテンプレート化しておきましょう。
例えば、「問題提起→共感→解決策の提示」といった導入文のパターンや、見出し構成の雛形を用意しておくだけで、思考の時間を大幅に削減できます。
テンプレートを活用することは、単なる時短に留まりません。
メディア全体の記事フォーマットが統一されることで、読者はどの記事を読んでも同じような安心感を得られ、ブランドイメージの向上にも繋がります。
品質の安定化と効率化を同時に実現できる、非常に有効な手法です。
AI・ツール自動化
近年、AIや各種ツールの進化により、記事執筆のプロセスは大きく変わりつつあります。
AIライティングツールを使えば、キーワードから見出し案を瞬時に生成したり、文章のたたき台を作成させたりすることが可能です。
これにより、アイデア出しや執筆の初動にかかる時間を劇的に短縮できます。
また、キーワード調査ツールや競合分析ツール、誤字脱字をチェックする校正ツールなども積極的に活用しましょう。
人間が時間をかけて行っていた単純作業や定型業務をツールに任せることで、ライターは「読者の心に響く表現を考える」といった、より創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。
チェックフロー最適化
チェックフローの最適化は、記事公開までの手戻りや待ち時間を削減し、プロセス全体をスムーズにするために重要です。
誰が、いつ、何をチェックするのかを明確に定めたルールを作りましょう。
例えば、「ライター執筆→編集者チェック→最終確認者」といった流れと、それぞれの担当範囲を定義します。
チェックリストを用意し、誤字脱字、事実確認、レギュレーション遵守といった項目を漏れなく確認できるようにするのも効果的です。
複数人でのダブルチェック体制を敷くことで、ミスの発見率が高まり、記事の品質向上にもつながります。
ツールを使って進捗状況を可視化し、ボトルネックになっている工程を特定・改善していくことも大切です。
記事執筆に役立つおすすめツール5選
ツールは「質・速・再現性」を支える縁の下の力持ちです。
本章では目的別に厳選し、導入効果と運用のコツを解説します。
CMS・執筆支援
WordPress(Gutenberg)は直感的操作でレイアウト自由度が高く、AIOSEOなどのプラグインによりタイトルとメタ説明を可視化できます。
キーワード調査
Ubersuggestは無料枠でも検索ボリューム、SEO難易度、関連KWを一覧取得できます。
KeywordGap機能を活用し、競合が未対応の「穴場KW」を抽出しましょう。
校正・校閲
Ennoは誤字脱字や二重否定、ら抜き言葉をクリック一つで検出できます。
読みやすさスコアを確認し、文章を定量的に改善しましょう。
画像作成
Canvaはブランドキットでロゴとカラーパレットを事前設定し、全アイキャッチへ自動適用できます。
社内外のデザイナーが混在してもビジュアルガイドラインを守れます。
分析・改善
Google Search Consoleは検索クエリ×CTR×平均順位をCSV出力できます。
Looker Studioと連携して期間比較ダッシュボードを作成し、CTR低下を色付きアラートで表示すると、担当者が即リライトへ着手できます。
記事執筆についてよくある質問
ライターに向いている人は?
好奇心旺盛で情報を探索・整理することが好きな方が向いています。
学習継続とフィードバック耐性が高いほど成長が期待できます。
記事ライティングとは何ですか?
検索意図を満たす情報を体系的に文章化し、読者の行動(購入・登録・共有)を促進するデジタルライティング手法です。
記事を執筆するときのルールは?
ペルソナ設定、一次情報と公的統計での裏付け、独自視点の追加、著作権・NDA順守、公開後のリライトが基本のルールです。
ライターは誰でもなれるの?
なれますが、成果を出し続けられる人は限られるでしょう。
基礎文章力とSEO知識は学習で習得可能で、成果を出すにはデータ分析と改善サイクルを継続的に回す習慣が不可欠です。
記事執筆のまとめ
この記事では、成果を出すための記事執筆の全貌を、具体的な流れから依頼方法、ライター選びのコツ、効率化テクニックまで幅広く解説しました。
記事執筆は、単なる文章作成ではなく、読者の悩みを解決し、ビジネス目標を達成するための戦略的な活動です。
成功のためには、「キーワード選定→競合調査・構成作成→情報収集→執筆→校正・改善」という一連のプロセスを丁寧に行うことが欠かせません。
また、リソースが限られる中で成果を最大化するためには、フリーランスや記事作成代行サービス、AIツールといった外部の力や技術を賢く活用する視点も重要です。
自社の状況に合わせて内製と外注を最適に組み合わせることで、品質、コスト、スピードのバランスを取りながら、効率的にコンテンツ資産を築いていけます。
本記事で紹介した知識やテクニックを実践し、読者からも検索エンジンからも愛される記事を作成することで、あなたのビジネスは着実に成長していくはずです。
まずは、最初の1記事のキーワード選定から始めてみましょう。