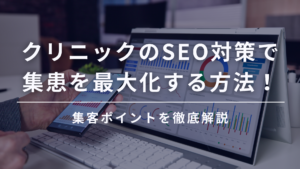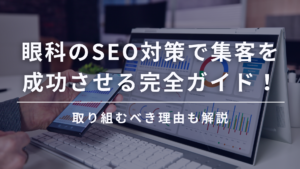AIを用いた構成作成とは?SEO対策・プロンプトをわかりやすく解説

「AIで記事の構成を作りたいけれど、どのツールを使えば良いかわからない」
「そもそもAIが作った構成で本当にSEO効果があるのか不安」
そんな悩みを抱えていませんか。
ただAIに任せるだけでは、誰でも作れるような質の低い記事になりかねません。
場合によっては、検索順位が上がらず、時間と労力を無駄にしてしまう可能性もあります。
この記事では、AIによる構成作成の基本から、具体的な手順、おすすめのツール比較、そしてSEOで成果を出すための秘訣まで、解説します。
最後まで読むことで、AIを賢く活用し、高品質な記事を効率的に生み出すノウハウを身につけられるでしょう。

AIを用いた構成作成とは?
AIを用いた構成作成とは、人工知能ツールを活用して記事の骨子となる見出し(H2、H3など)を自動で生成するプロセスを指します。
構成作成は、コンテンツ制作の初期段階で行う、質を左右する作業の一つです。
AIに構成を作成する主な狙いは、SEO(検索エンジン最適化)に強い記事を効率的に制作することです。
具体的には、AIが検索上位サイトの傾向やユーザーの検索意図を分析し、網羅性の高い構成案を短時間で作成します。
従来は担当者が手作業で行っていた、競合調査やキーワード分析の時間を、大幅に短縮できるのが大きな利点です。
AIに記事構成を任せることにより、ライターはより創造的な本文執筆や、独自の情報を盛り込むといった付加価値の高い作業に集中しやすくなります。
最終的に、ユーザーの満足度と検索エンジンの評価を両立させた高品質なコンテンツ作りを目指すことが、AIを用いた構成作成の定義であり狙いです。
AIを活用した構成作成のメリット・デメリット
AIの活用は構成作成を効率化する可能性がありますが、特性を理解することが大切です。
ここでは、AIを活用する上でのメリット、デメリット、そしてどのようなジャンルに向いているのかを解説します。
メリット
AIを活用する大きなメリットは、作業速度の向上です。
従来数時間かかっていた競合リサーチや見出しの抽出を、AIは数分で完了できます。
AIを用いることで、コンテンツ制作のリードタイムを大幅な短縮が可能です。
また、AIは指定されたキーワードに関連するトピックを網羅的に洗い出すため、人間では見落としがちな視点やキーワードの抜け漏れを防ぐ効果が期待できます。
結果、ユーザーの多様な検索意図に応える、より満足度の高い記事構成が実現しやすくなります。
さらに、AIは一定のルールに基づいて構成案を出力するため、品質のばらつきが少なく、誰が使ってもある程度高いレベルの構成を再現できる点も強みと言えるでしょう。
AIを活用することで、チーム全体でのコンテンツ品質の標準化が容易になります。
AI構成作成のメリット
- 作業速度の向上: リサーチと構成案作成にかかる時間を数分レベルに短縮。
- 網羅性の確保: 関連キーワードやトピックの抜け漏れを防止。
- 品質の一貫性: 担当者による品質のブレが少なく、一定のクオリティを維持しやすい。
- 高い再現性: 同じ指示であれば、誰でも同レベルの構成案を作成可能。
デメリット
一方、AIの構成作成にはデメリットも存在します。
懸念点の一つは、競合サイトの情報を参考にしているため、構成が似通ってしまい独自性が低下するリスクがあることです。
他サイトと同じような内容では、読者や検索エンジンに評価されにくくなる可能性があります。
また「ハルシネーション」と呼ばれる、AIが事実に基づかない情報を生成してしまう現象にも注意が必要です。
特に専門的な内容や固有名詞については、人間の目でのファクトチェックが重要になります。
さらに、多くのAIは学習データの時点が限られているため、最新のトレンドや法改正といった情報の鮮度が求められるテーマには対応できない場合があります。
常に最新情報を反映するには、人間の手による追加リサーチと修正が求められるでしょう。
AIで行う構成作成の手順
AIを使った構成作成は、正しい手順を踏むことで効果を最大化しやすくなります。
ここでは、初心者でも迷わないための4つのステップを具体的に解説します。
事前リサーチ:検索意図・競合・関連KW
まず、AIに指示を出す前に、人間による事前リサーチが非常に重要です。
ターゲットとするキーワードで検索するユーザーが「何を知りたいのか(検索意図)」を深く理解することが、良いコンテンツ作りの土台となります。
次に、そのキーワードで上位表示されている競合サイトを3〜5つほど確認しましょう。
どのような内容が評価されているのか、どのような見出しで構成されているのかを把握します。
そして、サジェストキーワードや関連キーワードをツールで洗い出し、ユーザーが他にどのような情報を求めているかをリストアップします。
「検索意図の理解」「競合分析」「関連KWの把握」という3つの情報が、AIへの的確な指示に繋がります。
▼キーワード選定について詳しく知りたい方は、この記事がおすすめ▼
AIを使ったKW選定方法とは?SEOに効く方法・ツール・プロンプトを紹介
構成作成:H2/H3骨子と順序設計
事前リサーチで得た情報を基に、AIに構成案の作成を指示します。
指示する時、ただ「〇〇の構成を作って」と依頼するだけでは、質の高い出力は期待しにくいでしょう。
「ターゲット読者」「検索意図」「含めてほしいキーワード群」「競合サイトの傾向」といった情報をプロンプト(指示文)に盛り込み、H2とH3からなる階層構造で出力するよう具体的に命じます。
AIが出力した構成案をそのまま使うのではなく、人間の目でチェックすることが大切です。
読者が読みやすいように見出しの順序を入れ替えたり、より分かりやすい言葉に修正したりする「順序設計」が、記事の品質を大きく左右します。
本文作成:見出し単位出力+加筆+要約
構成が固まったら、次は作成された構成案に基づいて本文を作成していきます。
記事全体を一度にAIに出力すると、内容が薄くなったり、話が逸れたりする傾向が見られます。
そのため、H2やH3といった見出し単位で区切り、一つずつ本文の生成を指示するのがおすすめです。
見出し単位で区切ることで、各見出しのテーマに沿った、より深く掘り下げた内容を出力させやすくなります。
AIが生成した文章は、あくまで下書きと捉えましょう。
ここに、自身の体験談や独自の考察、具体的な事例などを「加筆」することで、記事の独自性と専門性が高まります。
各見出しの最後には、内容をまとめる「要約」の一文を入れると、読者の理解を助けます。
推敲・調整:冗長削除・EEAT補強
最後に、記事全体を推敲し、最終調整を行います。
AIが生成した文章には、冗長な表現や不自然な言い回しが含まれていることがあります。
人が読んだ時に違和感感じる箇所を修正し、スムーズに読める文章に整えましょう。
また、特に重要なのが「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の観点からの補強です。
具体的には、専門家の監修情報を加えたり、公的機関のデータを引用して出典を明記したり、筆者自身の具体的な経験を盛り込んだりします。
こうした人間ならではの付加価値を加えることで、AIが作成した骨子を、検索エンジンや読者から評価されやすい高品質な記事へと昇華することができます。
AI対応の構成作成におすすめのツール比較
AIを活用した構成作成ツールは数多く存在し、それぞれに特徴があります。
ここでは、代表的なツールを比較し、あなたの目的に合った選び方を解説します。
| ツール名 | 特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| ラッコキーワード | キーワードリサーチに強く、関連KWや見出し抽出機能が充実 | SEOのキーワード調査から始めたい初心者 |
| Keywordmap | 構成作成から本文生成まで一気通貫。競合分析機能も強力 | 組織的にコンテンツ制作を行う中〜上級者 |
| ChatGPT / Gemini | 汎用性が非常に高く、自由な指示で多様な構成案を作成可能 | 様々な用途にAIを応用したい全てのユーザー |
| Notion AIなど | 普段使うドキュメントツール上でシームレスにAI機能を利用可能 | 既存のワークフローを崩さずに効率化したい人 |
ラッコキーワード:見出し作成支援
ラッコキーワードは、キーワードリサーチツールとして広く知られていますが、AIによる見出し作成支援機能も搭載しています。
指定したキーワードで上位表示されているサイトの見出しを一覧で抽出し、AIがそれらを整理・要約して構成案を提案してくれます。
ラッコキーワードの強みは、SEOの基本であるキーワード調査と構成作成の初期段階をスムーズに繋げられる点です。
サジェストキーワードや共起語の調査結果を見ながら構成案を練ることができるため、検索意図からのズレが少ない骨子を作りやすいのが特徴です。
まずはキーワードリサーチをしっかり行いたいSEO初心者の方におすすめです。
Keywordmap:構成〜本文まで一気通貫
Keywordmapは、より本格的なSEO対策を目指すための多機能ツールです。
市場調査や競合分析、キーワード選定、構成案作成、そしてAIによる本文生成まで、コンテンツマーケティングに役立つ工程を一つのツールで完結できるのが強みと言えます。
特に、競合サイトがどのようなキーワードで流入を獲得し、どのような構成で記事を作成しているかを詳細に分析できる機能は有用です。
データに基づいた戦略的な構成案を作成したい、あるいはチームで大量のコンテンツを効率的に制作したい法人や上級者に適しています。
ChatGPT / Gemini:ゼネラリスト型の応用
ChatGPTやGemini(旧Bard)といった対話型AIは、特定の機能に特化していませんが、汎用性の高さが魅力です。
プロンプト(指示文)を工夫することで、非常に柔軟な構成作成が可能です。
例えば「専門的なテーマについて、初心者にも分かるようなステップ形式の構成案を」といった、複雑な要望にも応えてくれることがあります。
自分なりのテンプレートや指示方法を確立することで、他のツールにはないオリジナリティあふれる構成を生み出せる可能性があります。
アイデア出しの壁打ち相手として活用できるツールです。
Notion AI・Googleスプレッドシート連携など
日々の業務でNotionやGoogleスプレッドシートを使っているなら、連携されたAI機能を活用するのも一つの手です。
これらのツールは、ドキュメント作成やタスク管理の流れの中で、シームレスにAIのサポートを受けられるのが利点です。
例えば、Notion AIを使えば、ブレインストーミングで出したアイデアを元に、その場で記事構成案を作成できます。
また、GoogleスプレッドシートとAPIを連携させれば、キーワードリストから一括で構成案を生成するといった自動化も可能です。
普段使っているツール上で作業を完結させたい、効率化を極めたい人に向いています。
AI活用の構成作成におけるSEO対策のポイント
AIで構成を作成するだけでは、SEOで勝ち続けることは難しいかもしれません。
AIの出力を土台とし、人間が戦略的な視点を加えることが必要です。
ここでは、検索上位を目指すための3つの重要なポイントを解説します。
検索意図と構成の一致性
SEOにおいて特に重要なのは、ユーザーの「検索意図」に応えることです。
AIが提案する構成案は、上位サイトの傾向をまとめたものの一つです。
提案された構成案が、本当にユーザーが知りたい情報と一致しているか、人間の目で吟味する必要があります。
例えば、「AI ツール おすすめ」で検索するユーザーは、単なるリストだけでなく、料金や機能の比較、選び方のポイントまで知りたいと考えるでしょう。
AIの構成案にユーザーの視点が抜けていれば、追記・修正することが望ましいです。
検索意図を深く読み解き、構成に反映することが、読者の満足度を高める第一歩です。
EEATの盛り込み方(一次情報・出典・体験)
現在のGoogleは、コンテンツの「経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)」を重視する傾向にあります。
AIだけでは生成が難しい、人間ならではの付加価値を構成段階から意識的に盛り込むことが重要です。
E-E-A-Tを構成に盛り込む具体例
- 経験(Experience): 「筆者が実際に使ってわかった〇〇のコツ」といった見出しを追加する。
- 専門性(Expertise): 専門家へのインタビューや監修者情報を入れる構成にする。
- 権威性(Authoritativeness): 官公庁や研究機関の公表データを引用する見出しを設ける。
- 信頼性(Trustworthiness): 運営者情報や問い合わせ先への導線を明確にする。
独自の体験談や信頼できる情報源を組み込むことで、記事の説得力と価値の向上が期待できます。
参考:品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加
内部リンクとクラスター設計
作成する記事がサイト内で孤立しないよう、戦略的に内部リンクを設計することも構成作成時に考えるべき重要な要素です。
一つの大きなテーマ(親記事)と、それに関連する詳細なテーマ(子記事)をグループ化する「トピッククラスター」を意識すると良いでしょう。
例えば「AI 構成作成」という親記事の構成を考える際は、「AI プロンプト」「AI ライティングツール 比較」といった子記事へのリンクをどこに配置するか計画します。
内部リンクを設計することにより、サイト全体のテーマ性が強まり、ユーザーは関連情報を回遊しやすくなり、サイト全体のSEO評価向上に繋がる可能性があります。
PAA・サジェストの活用場所
PAA(People Also Ask/他の人はこちらも質問)やサジェストキーワードは、ユーザーの具体的な疑問やニーズの宝庫です。
AIが生成した構成案に疑問を解消する要素を組み込むことで、よりユーザーの悩みに寄り添ったコンテンツになります。
例えば、構成案の中に「よくある質問(FAQ)」という見出しを設け、PAAで表示される質問と回答を盛り込むのが効果的です。
また、サジェストキーワードから見つかったニッチな悩みに対する見出しを追加することで、他のサイトにはない独自の切り口を提供できます。
AIの網羅性に、人間の細やかな視点を加えることが差別化のポイントになります。
AIベースの構成作成のプロンプト集(テンプレあり)
AIから質の高い構成案を引き出すには、的確なプロンプト(指示文)が鍵となります。
ここでは、コピーしてすぐに使えるテンプレートを目的別に紹介します。
構成作成テンプレート例
基本的な構成案を作成する際のテンプレートです。
[ ]の中をあなたの目的に合わせて書き換えてください。
# 指示
あなたはプロのSEOライターです。以下の条件に基づいて、SEOに強い記事構成案を作成してください。# 条件
・対策キーワード:[AI 構成作成]
・想定読者:[企業のWeb担当者。記事作成の効率化と品質向上に課題を感じている]
・読者の悩み:[AIの使い方がわからない、ツールの選び方がわからない、SEO効果があるか不安]
・記事のゴール:[読者がAIを使った構成作成の具体的な手順を理解し、自社で実践できるようになること]
・含めてほしいトピック:[メリット・デメリット、具体的な手順、おすすめツール、注意点、プロンプト例]
・競合サイトの傾向:[ツールの比較記事が多いが、SEO観点での深い解説が少ない]
・トーン&マナー:[専門的でありながら、初心者にも分かりやすい丁寧な言葉遣い]
・出力形式:
– H2とH3の階層構造で出力してください。
– 各見出しはユーザーの検索意図を反映した具体的なものにしてください。
本文出力テンプレート例
作成した構成案の見出し一つひとつに対して、本文を生成する際のテンプレートです。
# 指示
あなたはプロのSEO編集者です。以下の見出しと条件に基づいて、読者の理解を深めるための本文を作成してください。# 見出し
[H2: AIを活用した構成作成のメリット・デメリット・向き不向き]# 条件
・文字数:[600字程度]
・構成:PREP法(結論→理由→具体例→結論)を意識し、自然な文章で執筆してください。
・含めてほしい要素:
– メリットとして「速度」「網羅性」を挙げる。
– デメリットとして「独自性低下」「ハルシネーション」に触れる。
– 具体例として、AIが得意なジャンルと苦手なジャンルを比較する。
・ターゲット読者:[企業のWeb担当者]
・注意点:専門用語は避け、平易な言葉で解説してください。
品質チェック・リライト指示テンプレ
AIが生成した文章の品質をチェックし、修正を指示する際のテンプレートです。
# 指示
あなたは優秀な校正者です。以下の文章をレビューし、修正案を提案してください。# 対象文章
[(AIが生成した文章をここに貼り付ける)]# チェック項目
1. 誤字脱字や不自然な日本語表現はないか?
2. 主張に一貫性はあるか?論理が破綻していないか?
3. E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点で不足している要素はないか?
4. より読者の心に響く、魅力的な表現にできないか?# 出力形式
・修正が必要な箇所を具体的に指摘してください。
・修正後の文章案を提示してください。
AIを取り入れた構成作成の効果測定と改善サイクル
AIを活用して記事を作成したら、それで終わりではありません。
効果を測定し、改善を繰り返していくことがSEOの成果を最大化するために重要です。
ここでは、効果測定の具体的な方法について解説します。
主要KPI(順位・表示回数・CTR・滞在・回遊・CV)
まず、記事の成果を測るための主要な指標(KPI)を理解しましょう。
主要KPIの数値を定期的に観測することで、コンテンツの健康状態を把握できます。
| KPI | 内容 | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 検索順位 | 対策キーワードでのGoogle検索結果の掲載順位 | 順位が上がるほどユーザーの目に留まりやすくなる |
| 表示回数 | 検索結果に記事が表示された回数 | 記事がどれだけ検索需要にマッチしているかの指標 |
| CTR | 表示回数のうちクリックされた割合 | タイトルやディスクリプションの魅力度を示す |
| 滞在時間 | ユーザーが記事を読んでいた平均時間 | コンテンツの満足度や読みやすさの指標 |
| 回遊率 | 1人のユーザーがサイト内の別ページを見る割合 | 内部リンクが機能し、サイト全体に興味を持たれているかを示す |
| CV | 商品購入や問い合わせなど、最終的な成果の数 | ビジネス上の目標を達成できているかの最終指標 |
計測設計(SearchConsole/Analytics)
KPIを計測するためには、「Googleサーチコンソール」と「Googleアナリティクス」の導入が一般的に推奨されます。
- Googleサーチコンソール:主に検索エンジン上でのパフォーマンスを計測します。
∟検索順位、表示回数、CTRといった、ユーザーがサイトに訪れる前のデータを分析するのに役立ちます。
∟どのキーワードで評価されているか、改善すべき点はどこかを探るために使用します。 - Googleアナリティクス:サイトに訪れた後のユーザーの行動を計測します。
∟滞在時間、回遊率、コンバージョン(CV)といったデータを分析できます。
∟コンテンツがユーザーの期待に応えられているか、ビジネス目標に貢献しているかを評価するために使用します。
2つのツールを連携させ、定期的にレポートを確認する体制を整えることが望ましいです。
ABテストとベンチマーク
より効果的な改善を行うためには、ABテストが有効です。
例えば、AIが提案した2パターンのタイトルを用意し、どちらがより高いCTR(クリック率)を獲得できるかを試すといった方法です。
見出しの表現や構成の順序を変えてみて、どちらが滞在時間が長くなるかを比較するのも良いでしょう。
また、自社の過去の記事や競合サイトをベンチマーク(基準)として設定することも役立ちます。
「AI導入前と比べて滞在時間が10%向上した」「競合サイトの平均CTRに近づける」といった具体的な目標を持つことで、改善活動がより戦略的になります。
AIによる効率化で生まれた時間を、こうした分析と改善のサイクルに充てることが成功に繋がるでしょう。
AIによる構成作成の注意点
AIは便利なツールですが、利用にはいくつかの注意点があります。
特に著作権、品質、そしてハルシネーションのリスクを正しく理解し、対策を講じることが大切です。
著作権や引用ルール
AIが生成する文章は、インターネット上の膨大なテキストデータを学習して作られています。
結果、意図せず既存のコンテンツと酷似した表現や文章が生成されてしまう可能性があります。
生成された文章をそのまま公開すると、著作権侵害にあたるリスクが高いです。
AIが生成した文章はコピーコンテンツチェックツールで確認することをおすすめします。
また、他のサイトや文献から情報を引用する際は、引用元を明記し、引用のルールを守ることが基本的なマナーです。
AIはアシスタントであり、最終的な文責は公開者自身にあることを念頭に置きましょう。
ハルシネーション対策と検証方法
ハルシネーションとは、AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象です。
特に、統計データ、法律、専門的な技術情報など、正確性が求められる内容については、ハルシネーションのリスクが伴います。
対策として、AIが生成した情報は鵜呑みにせず、一次情報源でファクトチェックを行う習慣をつけることが大切です。
例えば、統計データであれば官公庁の公式サイト、医療情報であれば専門機関の発表といった、信頼できる情報源で裏付けを取ることが非常に重要です。
検証作業を怠ると、サイト全体の信頼性を損なう可能性があります。
構成の独自性確保のコツ
AIによる構成作成は、上位サイトの傾向を分析するため、内容が似通ってしまう傾向があります。
他サイトとの差別化を図り、独自性を確保するためには、以下のような工夫が考えられます。
- 一次情報を加える:独自のアンケート調査結果や、自社しか持たないデータ、筆者自身の体験談などを盛り込む。
- 独自の切り口を設ける:他のサイトが触れていないニッチなトピックや、異なる視点からの解説を加える。
- ペルソナを深く設定する:「〇〇に悩む30代女性」のように、ターゲット読者をより具体的に設定し、響く言葉や構成を意識する。
AIに100%依存するのではなく、AIの提案を「壁打ちの相手」と捉え、人間の創造性や経験を掛け合わせることが、独自性の高いコンテンツを生み出すポイントです。
AIを使った構成作成に関してよくある質問
AIによる構成作成について、多くの方が抱く疑問にお答えします。
AIで作った構成でも上位表示できる?
適切に使えば上位表示の可能性は十分にあります。
重要なのは、AIが作成した構成案をそのまま使うのではなく、人間の手で「検索意図との一致性」「E-E-A-Tの補強」「独自性」といった要素を加えて磨き上げることです。
AIをリサーチやアイデア出しを高速化するアシスタントと位置づけ、最終的な品質を人間が担保することで、SEOに強いコンテンツを作成しやすくなります。
キーワード選定までAIで完結できる?
ある程度は可能ですが、完全にAI任せにするのはあまり推奨されません。
AIは関連キーワードの洗い出しや検索ボリュームの調査に役立ちます。
しかし、AIが選定したキーワードが自社のビジネス目標にどう繋がるかといった戦略的な判断は、最終的に人間の知見が求められます。
AIの提案を参考にしつつ、事業戦略と照らし合わせてキーワードを決定するのが良いでしょう。
無料と有料ツールの違いは?
無料ツール(ChatGPTの無料版など)でも基本的な構成作成は可能ですが、有料ツールはより高機能でSEOに特化していることが多いです。
主な違いは以下の通りです。
| 無料ツール | 有料ツール | |
|---|---|---|
| 機能 | 汎用的な対話が中心 | 競合分析、検索ボリューム調査、共起語抽出などSEO特化機能が豊富 |
| 情報 | 学習データが古い場合がある | 最新の検索トレンドを反映していることが多い |
| 精度 | 指示が曖昧だと質が安定しない | データに基づいた高精度な構成案を生成しやすい |
| サポート | 基本的になし | 専門のサポートを受けられる場合がある |
まずは無料で試してみて、より高度な分析や効率化が必要になったら有料ツールを検討するのが一つの方法です。
初心者でも使える構成作成テンプレートは?
本記事の「AIベースの構成作成のプロンプト集」で紹介したテンプレートが、初心者の方でも使いやすい基本的な型になります。
大切なのは、[ ]で示した部分(キーワード、想定読者、記事のゴールなど)を、ご自身の目的に合わせて具体的に記述することです。
事前情報をAIに与えることで、出力される構成案の精度が向上しやすくなります。
AI活用の構成作成で高品質な記事制作をしよう【まとめ】
本記事では、AIを用いた構成作成の基本から、具体的な手順、おすすめツール、そしてSEOで成果を出すための応用テクニックまでを網羅的に解説しました。
AIによる構成作成は、リサーチ時間を短縮し、トピックの抜け漏れを防ぐなど、コンテンツ制作を効率化する上で強力な手法となり得ます。
しかし、AIの提案をそのまま利用するだけでは、独自性のない低品質な記事に陥る可能性も考慮するべきです。
AIは「優秀なアシスタント」と理解しておく必要があります。
AIが生成した骨子を土台に、人間の手で検索意図を深く読み解き、独自の経験や専門性(E-E-A-T)を加え、戦略的な内部リンクを設計する。
「AIとの協業」が、これからのSEOコンテンツ制作において、より重要になってくるでしょう。
本記事で紹介した手順やプロンプトを活用し、AIを賢く使いこなすことで、あなたのコンテンツ制作は新たなステージへと進化する可能性があります。
ぜひ、今日から実践してみてください。