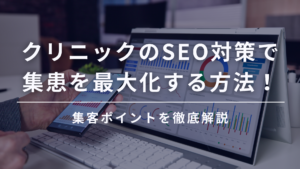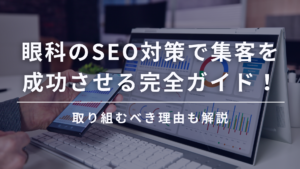AIを活用した執筆方法!おすすめツール比較と具体的なAI執筆の方法を徹底解説
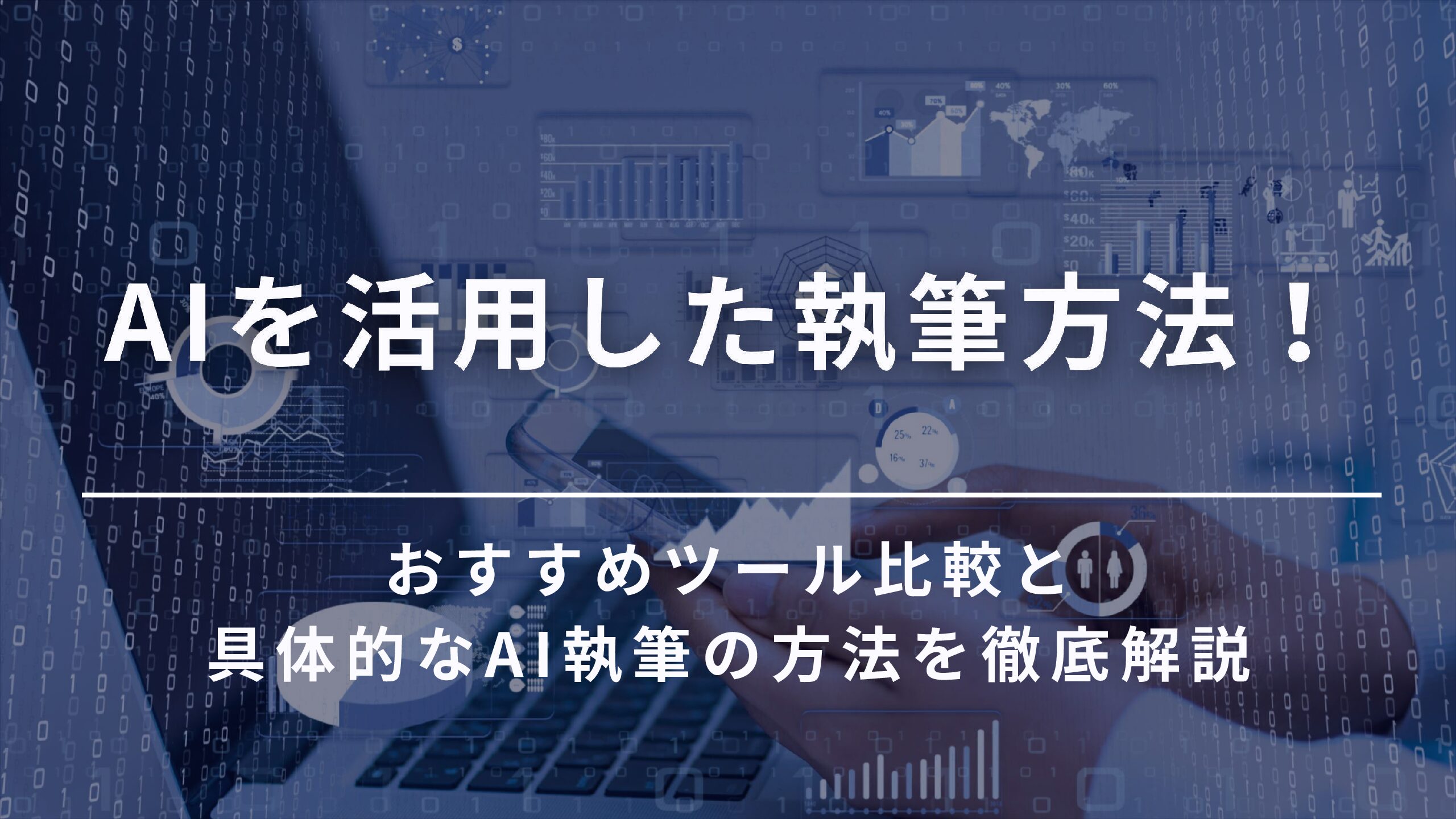
「記事の執筆に時間がかかりすぎる」「新しいアイデアがなかなか浮かばない」
コンテンツ制作に携わる多くの方が、執筆に関する悩みを抱えているのではないでしょうか。
締め切りに追われ、質の高いコンテンツを継続的に生み出すプレッシャーは大きいものです。
もし、現状の非効率な作業を続ければ、競合サイトとのコンテンツ競争で後れを取ってしまうかもしれません。
しかし、AIを活用すれば、執筆に関する悩みは解決できます。
AIを執筆のパートナーとすることで、作業時間を大幅に短縮し、創造性を刺激する新たなアイデアを得られるでしょう。
今回の記事では、AIを使った具体的な執筆手順から、目的に合わせたツールの選び方、そして気になるSEOや著作権の注意点まで網羅的に解説します。

AIを活用した執筆とは?仕組みとできること
AIを活用した執筆とは、人工知能、特に「大規模言語モデル(LLM)」を用いて文章を自動で生成したり、執筆作業を補助したりすることです。
大規模言語モデルは、脳の神経回路網を模した「ニューラルネットワーク」という技術をベースにしています。
特に「Transformer」と呼ばれる仕組みが画期的で、文中の単語同士の関連性を効率的に学習できるようになりました。
AIの画期的な仕組みにより、文脈を深く理解し、人間が書いたような自然な文章の生成が可能になったのです。
AI執筆でできることは非常に多岐にわたります。単に文章を作るだけでなく、執筆プロセス全体をサポートする多様な能力を持っています。
- 文章の新規作成:ブログ記事、メール、SNS投稿、プレスリリース、広告文など
- リライト・要約:既存の文章を異なる表現で書き直したり、長文を短い要約にまとめたりする
- ブレインストーミング:記事のタイトル案、キャッチコピー、企画のアイデア出し
- 構成案の作成:テーマを伝えるだけで、記事全体の骨子となる見出し構成を提案する
- 翻訳:日本語から英語、英語から日本語など、多言語間の高精度な翻訳
- 校正・校閲:誤字脱字のチェックや、より自然な表現への修正提案
- 専門的な文章生成:簡単なプログラムコードの生成、法律文書の草案作成など
このようにAIは、執筆に関するあらゆる工程を効率化し、サポートする強力なアシスタントとなり得るでしょう。
AIを用いた執筆のメリット
AIを執筆に取り入れることで、具体的にどのような恩恵があるのでしょうか。
AI執筆の利点を理解すれば、ご自身の作業がどのように改善されるか具体的にイメージできるようになるでしょう。
ここでは、生産性の向上やアイデア創出の観点から、AI執筆がもたらす主なメリットを解説します。
時間を短縮できる
AI執筆の最大のメリットは、執筆にかかる時間を劇的に短縮できる点にあります。
AIは、リサーチや構成案の作成、文章の叩き台生成といった時間を要する作業を、わずか数分で完了させることが可能です。
例えば、これまで数時間かかっていたブログ記事の下書きが、AIへの適切な指示によって1時間程度で完成するケースも少なくありません。
AI活用によって生まれた時間的な余裕を、より創造的な作業やファクトチェック、推敲といったコンテンツの質を高める工程に充てられるようになるでしょう。
発想を補助してくれる
自分一人では思いつかないような、新しいアイデアや視点を得られることもAI執筆の大きなメリットです。
記事のテーマに行き詰まった際に、AIにタイトル案を複数出してもらったり、異なる切り口からの構成案を提案させたりすることで、発想の幅を広げられます。
AIは学習した膨大なデータの中から、人間が気づきにくい意外な関連性を見つけ出すことがあります。
AIが持つデータ分析能力を活用することで、マンネリ化しがちなコンテンツに新鮮な風を吹き込み、創造性の壁を乗り越えるための強力なサポート役となってくれるでしょう。
大量コンテンツの生成ができる
AIは、一度に多くのコンテンツを効率的に生成することを得意としています。
特定のテンプレートや指示に基づいて、類似したパターンの文章をスピーディーに量産できるため、メディアの更新頻度向上に大きく貢献します。
例えば、ECサイトの商品説明文や、SNSの定期的な投稿、メールマガジンの文面など、フォーマットがある程度決まっているコンテンツ作成に非常に有効です。
人手だけでは困難だった大量のコンテンツ制作をAIが担うことで、安定した情報発信を実現し、ユーザーとの接点を増やせるようになる可能性があります。
品質の均一化ができる
コンテンツの品質を一定に保てる点も、AI活用の見逃せないメリットです。
特に複数人のチームでメディアを運営している場合、ライターによって文章のスタイルや品質にばらつきが生じがちです。
AIに共通のプロンプトやトーン&マナーを指示することで、誰が使っても一定の品質を保った下書きを生成できます。
個人差が無くなることでメディア全体の統一感を演出し、ブランドイメージを維持しやすくなるでしょう。
修正や編集にかかる時間も削減できるため、チーム全体の生産性向上にもつながります。
AIを用いた執筆のデメリット
非常に便利なAI執筆ですが、万能というわけではありません。
AI執筆の限界や注意点を理解しておくことは、トラブルを未然に防ぎ、より質の高い文章を作成する上で不可欠です。
AIと賢く付き合っていくために、知っておくべきデメリットを具体的に見ていきましょう。
誤情報を含む可能性がある
AIが生成する文章には、事実と異なる情報が含まれている可能性がある点に注意が必要です。
AIは学習データに基づいて文章を生成しますが、AIが学習する元データが古かったり、誤りを含んでいたりすることがあります。
また、文脈を完全に理解しているわけではないため、もっともらしい嘘(ハルシ-ション)を生成してしまうことも少なくありません。
特に、専門的な知識や最新の情報を扱う分野では、誤情報のリスクが高まる傾向が見られます。
そのため、AIが生成した文章は必ず人間の目でファクトチェックを行い、情報の正確性を担保することが不可欠と言えるでしょう。
同じ表現を繰り返す
AIには、特定の言い回しや構文を繰り返す癖が見られることがあります。
生成された文章を読むと、表現が単調で、どこか機械的な印象を受ける場合があるのは、AIの特性が理由です。
例えば、「~することができます」「~と言えるでしょう」といった表現が不自然に多用されることがあります。
表現が単調な文章は、読者に飽きられやすく、内容が頭に入りにくいかもしれません。
AIが作成した文章はあくまで下書きと捉え、人間が推敲を行うことで、より自然でリズム感のある、魅力的な表現に磨き上げる作業が重要になります。
普段使わない単語が使われる
AIは、学習データに含まれる書き言葉や専門用語の影響を強く受けるため、日常的にはあまり使わない硬い表現や、不自然な単語を使うことがあります。
読者層によっては、難解な言葉が使われていることで、内容の理解が妨げられてしまうかもしれません。
例えば、より平易な言葉で説明できる場面で、あえて難しい漢語表現を使ってしまうケースなどが見られます。
コンテンツのターゲットとなる読者を常に意識し、その人たちに合わせた適切な言葉遣いに修正していく配慮が、最終的な品質を高める上で求められるでしょう。
創造性の欠如と独自性の喪失
AIは、あくまで学習したデータの中にあるパターンを再構築しているに過ぎません。
そのため、真に独創的なアイデアや、深い洞察に基づいた意見を生み出すことは困難です。
AIが生成する文章は、平均的で無難な内容に落ち着きやすい傾向があります。
AIに頼りすぎると、どのサイトを見ても同じような内容が書かれている「没個性的なコンテンツ」を生み出してしまうリスクがあります。
書き手自身のユニークな視点や経験談といった一次情報を加えることで初めて、他のコンテンツとの差別化が図れることを忘れてはなりません。
AIを使った執筆のやり方と手順
AIを執筆に導入する際、どのようなステップで進めればよいのでしょうか。
ここで紹介する手順に沿って作業することで、初心者の方でもスムーズにAIを活用した執筆ができます。
AIの能力を最大限に引き出すための具体的なステップを確認し、効率的な執筆プロセスを構築しましょう。
STEP1:目的と構成を考える
AI執筆を始めるにあたり、最も重要なのが目的と構成を明確にすることです。
AIは具体的な指示がなければ、書き手の意図を正確に汲み取ることができません。
「誰に、何を伝え、どのような行動を促したいのか」という記事のゴールを最初に設定しましょう。
そして、設定したゴールから逆算して、どのような情報を、どのような順番で伝えるべきか、見出しレベルの構成案を作成します。
記事の骨子をしっかりと固めることが、手戻りのない効率的なAI執筆を実現するための最初のステップとなります。
STEP2:プロンプトで叩き台を生成する
記事の骨子が決まったら、作成した構成案に基づいてAIに文章の叩き台を生成させます。
文章生成の際に重要になるのが、「プロンプト」と呼ばれるAIへの指示文です。
プロンプトの質が、生成される文章の質を大きく左右します。
悪いプロンプトの例:
AI執筆のメリットを書いて。
→これでは抽象的すぎて、一般的で深みのない文章が生成される可能性が高いです。
良いプロンプトの例:
あなたはプロのWebライターです。企業のブログ担当者(30代)に向けて、「AI執筆のメリット」というテーマで記事を執筆します。以下の見出しについて、PREP法を用いて、メリットが具体的に伝わるように各300字程度で解説してください。
#見出し
- 時間を短縮できる
- 発想を補助してくれる
役割、読者、テーマ、形式、文字数などを具体的に指定することで、AIは書き手の意図をより正確に理解し、質の高い文章を生成しやすくなります。
STEP3:肉付けと編集・校正を行う
AIが生成した文章は、あくまで「叩き台」です。
そのまま公開できる品質であることは稀なため、人間の手による編集作業が必要です。
AIの文章は無機質で具体性に欠けることがあるため、自身の体験談や具体的なエピソードを加えて肉付けを行いましょう。
編集・校正を行う際は、以下のチェックポイントを意識すると品質が向上します。
- 情報の正確性:専門的な内容や数値データに誤りはないか。
- ペルソナへの適合:設定した読者層に合った言葉遣いやトーンになっているか。
- 独自性と共感性:書き手自身の体験談や独自の視点が盛り込まれているか。
- 論理的な一貫性:文章全体の主張に矛盾がなく、スムーズに流れているか。
- 文章のリズム:一文が長すぎないか、同じ文末表現が続いていないか。
STEP4:SEO・一次情報・出典を補強
最後に、記事の価値をさらに高めるための仕上げを行います。
SEOを意識する場合は、狙っているキーワードや関連キーワードを不自然にならないように盛り込みます。
また、AIだけでは生成できない「一次情報」を加えることが非常に重要です。
自身の独自の経験や専門家としての知見、アンケート調査の結果などを追記することで、記事の信頼性と独自性が格段に向上します。
公的なデータや論文を引用した場合は、必ず出典を明記しましょう。
SEOや一次情報を補強する最終工程が、他のコンテンツとの差別化を図り、読者と検索エンジンの双方から評価されるための鍵となります。
AIでの執筆に適したおすすめツール比較
現在、多種多様なAI執筆ツールが存在し、それぞれに特徴があります。
あなたの目的に合った最適なツールを見つけるための比較情報を提供します。
各ツールの強みを理解し、自身の執筆スタイルに合ったツールを選びましょう。
長文生成に強い:ChatGPT、Claude、Gemini
ブログ記事やレポートなど、まとまった量の文章を生成したい場合には、汎用的な大規模言語モデルを搭載したツールが適しています。
代表的な3つのツールにはそれぞれ特徴があります。
| ツール名 | 開発元 | 特徴 |
|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | 最も有名で汎用性が高い。豊富な情報量と自然な対話能力が強み。プラグインで機能拡張も可能。 |
| Claude | Anthropic | 長文の読解・生成能力に定評がある。より丁寧で倫理的な回答を生成する傾向が見られる。 |
| Gemini | Google検索との連携により、最新の情報に基づいた回答が得意。マルチモーダル機能も強力。 |
紹介したツールは、いずれも無料プランから試すことができるため、実際に使い比べてみて、自分の目的に合ったものを見つけるのがよいでしょう。
SEO対応に強い:国産ツールの活用ポイント
SEOコンテンツの作成を主目的とする場合、日本市場向けに開発された国産ツールが強力な選択肢となります。
国産のSEO対応ツールは、日本語のキーワード分析や検索意図の把握、競合サイトの分析といった、SEOに特化した機能を搭載していることが多いです。
例えば、「SAKUBUN」や「Catchy」といったツールは、キーワードを入力するだけでSEOに強いとされる構成案や見出しを自動で提案してくれます。
海外製ツールと組み合わせることで、リサーチから執筆までの一連の作業をさらに効率化できる可能性があります。
▼キーワード選定について詳しく知りたい方は、この記事がおすすめ▼
AIを使ったKW選定方法とは?SEOに効く方法・ツール・プロンプトを紹介
小説創作向け:AIのべりすと、AI Buncho
小説やシナリオといったクリエイティブな執筆活動には、物語の生成に特化したツールが役立ちます。
物語の生成に特化したツールは、キャラクター設定や世界観を反映させながら、物語の続きを自動で生成してくれる機能を持っています。
代表的なツールとして「AIのべりすと」や「AI Buncho」が挙げられます。
小説創作向けのツールは、執筆に行き詰まった際のアイデア出しや、物語の展開をサポートする壁打ち相手として、多くの創作者に活用されているようです。
特定用途向けツール(画像生成・リサーチ補助など)
執筆作業は文章作成だけではありません。
アイキャッチ画像の作成や情報収集も重要な工程です。
「Midjourney」や「Stable Diffusion」といった画像生成AIを使えば、記事の内容に合ったオリジナルの画像を短時間で作成できます。
また、「Perplexity AI」のような対話型の検索エンジンは、情報源を明記しながら質問に答えてくれるため、リサーチ作業の効率を大幅に向上させるでしょう。
選び方のポイント(日本語精度/UI/料金)
数あるツールの中から自分に合ったツールを選ぶ際は、以下の3つのポイントを意識するとよいでしょう。
- 日本語の精度:ツールによって日本語の自然さや語彙力に差があります。無料プランなどを活用し、生成される文章の品質が自分の求めるレベルにあるかを確認しましょう。
- UI(使いやすさ):操作画面が直感的で、ストレスなく使えるかどうかも重要な要素です。毎日使うツールだからこそ、自分にとって使いやすいインターフェースのツールを選びたいところです。
- 料金体系:料金プランは様々です。毎月一定の文字数まで生成できる「文字数課金」、機能制限なく使える「月額固定」などがあります。無料プランでどこまで使えるか、有料プランのコストパフォーマンスはどうかを比較検討しましょう。
AIを活かした執筆のSEO・著作権の注意点
AI執筆を本格的に活用する上で、ルールやリスクの理解は避けて通れません。
特に、Googleからの評価や法律に関わる問題は、コンテンツを公開する上で必ず押さえておくべきポイントです。
安全かつ効果的にAIを活用するために、必要な知識を身につけましょう。
Googleの評価:E-E-A-Tと品質ガイドライン
Googleは、コンテンツがAIによって生成されたかどうか自体を問題にはしていません。
重要なのは、コンテンツが読者の役に立つ高品質なものであるかという点です。
Googleは品質評価の基準として「E-E-A-T」という概念を重視しています。
- Experience(経験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trust(信頼性)
Googleは「有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成」に関するヘルプページで、コンテンツが独自の分析や深い情報を提供しているかを評価すると明記しています。
AIを使って作成した場合でも、最終的に人間が編集・監修し、E-E-A-Tを満たすことで、Googleから高く評価される可能性があります。
AI検出ツールの精度と限界
AIが生成した文章かどうかを判定する「AI検出ツール」が存在しますが、ツールの精度は100%ではありません。
AI検出ツールは、文章の統計的な特徴からAIらしさを判定するため、人間が書いた文章をAI製と誤判定したり、その逆のケースも起こり得ます。
ツールの判定結果に一喜一憂するのではなく、あくまで参考情報の一つとして捉えるのが賢明です。
検出を回避するテクニックを考えるよりも、前述のE-E-A-Tを高め、読者にとって価値のある独自のコンテンツを作成することに注力する方が、本質的な対策と言えるでしょう。
著作権・倫理問題と引用のルール
AIが生成した文章の著作権については、まだ法的に明確に定まっていない部分が多く、議論が続いています。
現状では、AI自体に著作権は認められず、生成プロセスにおける人間の創作的な寄与がどの程度あったかが論点となるようです。
注意すべきは、AIが学習データに含まれる既存の著作物を意図せずコピーし、著作権侵害となる文章を生成してしまうリスクです。
生成された文章は必ず内容を確認し、他のコンテンツと酷似していないかチェックする必要があります。
また、各AIツールの利用規約を確認し、生成物の商用利用が許可されているかどうかも必ずチェックしましょう。
情報を引用する際は、通常の記事作成と同様に、引用元を明記するなどのルールを遵守することが求められます。
AIを用いた執筆に関してよくある質問
AI執筆を始めるにあたり、多くの方が抱くであろう疑問や不安についてお答えします。
疑問や不安を解消し、安心してAIを日々の執筆活動に取り入れていきましょう。
AIを用いた執筆は検索順位に影響する?
AIを使用したこと自体が、直接的に検索順位を下げる原因になる可能性は低いと考えられます。
Googleが一貫して重視しているのは、コンテンツの「品質」です。
AIを利用して作られた低品質で独自性のないコンテンツが検索順位の操作を目的としていると判断されれば、評価が下がることはあり得ます。
逆に、AIを補助的に活用し、読者の検索意図を満たす有益なコンテンツを作成すれば、良い評価につながるでしょう。
AIを使った執筆は検出される?回避策は?
AI検出ツールの精度は完璧ではありませんが、AIが生成した文章の特徴を捉えて検出される可能性はあります。
しかし、検出を回避すること自体を目的とするのは本質的ではありません。
重要なのは、AIが生成した文章をそのまま使うのではなく、自身の言葉で加筆・修正し、独自の視点や一次情報を加えることです。
そうすることで、結果的にAIらしさは薄まり、オリジナリティのある価値の高いコンテンツになるでしょう。
AIを活用した執筆のプロンプト作成のコツは?
AIから質の高い回答を引き出すには、プロンプト(指示文)の工夫が鍵となります。
以下の要素を盛り込むと、意図した通りの文章が生成されやすくなります。
- 役割の指定:例「あなたはプロの編集者です」
- 目的の明示:例「この記事の目的は、初心者にAI執筆のメリットを伝えることです」
- 読者設定:例「読者はコンテンツ制作の担当者です」
- 形式の指示:例「箇条書きで」「PREP法で」「表形式で」
- 制約条件:例「300字以内で」「専門用語は避けて」
役割指定や目的明示といった要素を組み合わせ、できるだけ具体的で明確な指示を出すことが、AIをうまく使いこなすコツです。
AI執筆のスキルを向上させるにはどうすればいいですか?
AI執筆のスキルは、意識的に学習し実践することで向上します。
まず、質の高い出力を引き出すための「プロンプトエンジニアリング」を学ぶことが有効です。
様々な指示の出し方を試し、AIの反応を見ることでコツが掴めます。
また、複数のAIツールを実際に使ってみて、それぞれの癖や得意分野を理解することも重要です。
そして何よりも、AIが生成した文章を徹底的に編集・リライトする練習を繰り返すことで、AIの文章を活かしつつ独自の価値を付加する能力が磨かれるでしょう。
無料と有料、どちらが向いている?
どちらが向いているかは、利用目的と頻度によります。
| 無料プランが向いている人 | 有料プランが向いている人 |
|---|---|
| ・簡単な文章作成やアイデア出しが目的 ・たまにしか使わない ・まずはAI執筆を試してみたい |
・長文の記事を頻繁に作成する ・最新、高性能なモデルを使いたい ・より高度な機能(画像生成など)も使いたい |
まずは無料プランから始めてみて、機能や生成量に物足りなさを感じたら有料プランへの移行を検討するのがおすすめです。
AIを活用した執筆を成功させるポイント【まとめ】
本記事では、AIを活用した執筆の具体的な方法から、メリット・デメリット、おすすめのツール、そしてSEOや著作権に関する注意点までを網羅的に解説しました。
AI執筆は、作業時間を大幅に短縮し、新たなアイデアの創出を助ける非常に強力なツールです。
ブログ記事の作成から日々の業務連絡まで、幅広いシーンでの活躍が期待できるでしょう。
しかし、AI執筆には誤情報のリスクや表現の画一性といったデメリットも存在します。
AIが生成した文章を鵜呑みにせず、必ず人間の手でファクトチェックや編集、そして独自の価値(経験や専門性)を加えることが不可欠です。
Googleの品質ガイドラインであるE-E-A-Tを意識し、読者にとって本当に役立つコンテンツ作りを目指す姿勢が、これまで以上に重要になります。
ChatGPTやClaude、国産のSEO特化ツールなど、目的によって最適なツールは異なります。
各ツールの特徴を理解し、自分に合ったツールを選ぶことが成功の鍵です。
AIを単なる「自動化ツール」ではなく、思考を深め、創造性を高めるための優秀な「パートナー」として賢く使いこなし、コンテンツ制作をさらに加速させていきましょう。